【農業の現場から学ぶ】「涼しい夏」の5月管理編に見る、現代農業のリアルと希望
みなさん、こんにちは。今回は、吉村農園さんのYouTube動画「第795回 5月の管理編」について、感想と考察をお届けします。
一見すると地味に見える「5月の管理」というテーマ。しかし、その中には、農業の現場にある“知恵”と“経験”、そして“変革”の兆しが凝縮されていました。農業に従事する皆さんはもちろん、経営やマーケティングに関心のある方にも参考になる要素が詰まっています。
「春」ではなく「涼しい夏」──気候変動に対応する現場の知恵
まず、動画冒頭で吉村さんが語っていた「5月は春ではなく“涼しい夏”だ」という一言。この発言には、農業者としての深い観察と現実的な対応力が表れていました。
10年前の教科書には「春」と書かれていても、現場はそうではない。5月にもかかわらず30度近い日も珍しくない昨今、教科書通りの作業では作物も人も守れない。この発想の転換は、まさに現場第一線に立つ人間にしかできない判断です。
「50〜60%の遮光率で関連者を張るべし」という具体的なアドバイスも、実体験に基づくリアルな提案。農業経営者として、こうした臨機応変さは極めて重要です。
収穫ハウス vs 育苗ハウス──二つのフェーズで異なる戦略を
5月は「収穫の終盤」と「育苗の始まり」が交差する月。だからこそ、二つのハウスで求められる戦略は大きく異なります。
◼ 収穫ハウス:アザミウマとカメムシに要注意
収穫ハウスでの管理ポイントとして挙げられていたのは、アザミウマとカメムシへの対策。特に「収穫を長く続ける場合の病害虫管理」は、利益とコストのバランスをどうとるかという経営判断に直結します。
面白いのは「カメムシは薬剤登録がないから、来ないことを祈るしかない」という一言。これは単なる諦めではなく、「防げるリスクと防げないリスクを見極める」冷静な分析です。
中小農家が限られたリソースで戦うには、すべてを完璧に管理するのではなく、「どこまでやるか」の線引きが重要。その点、吉村さんは「収穫を続けるならアザミウマ対策を定期的に」「カメムシは早期に兆候を捉えて撤退判断も」といった、リスクマネジメントの好例を示しています。
◼ 育苗ハウス:5月から始まる新たな戦い
一方で、育苗ハウスに関しては「本格的なスタートを切る月」として、より入念な準備が必要です。
特にランナー受け作業は、来シーズンの出来を左右する重要工程。ここで印象的だったのは、「今年からポットでのランナー受けに切り替える」という一言。これは、既存のやり方をただ踏襲するのではなく、試行錯誤を重ねながら最適解を模索している姿勢の表れです。
また、完水頻度や薬剤散布(殺菌・殺虫)に関する具体的な数値(例:10日に1回)も非常に実用的。視聴者にとって「今日から真似できる」ノウハウが詰まっています。
イベント現場での気づき:マーケティングの現場力
動画後半では、当期市イベントでの出展体験と、その中での学びが語られていました。
特に印象的だったのが、「リンゴジャムの販売手法」への言及。試食を“食パンにのせて提供する”というだけで、体験の質が格段に上がる。これにはマーケティングの本質が詰まっています。
つまり「五感を使って、ストーリーごと商品を伝える」。これは農産物の直売や加工品販売にも活かせる視点です。単に「美味しいです」ではなく、「どんなシーンで」「誰と食べるのか」「どんなこだわりがあるのか」といった“文脈”を伝えることで、購入体験は劇的に変わります。
現場での気づきを、こうして自分の仕事に取り入れようとする姿勢──ここにも吉村さんの経営者マインドが垣間見えました。
お客さまとの交流から生まれる力
また、視聴者やイベント来場者との交流エピソードも非常に心温まるものでした。
30分〜1時間かけて話したという母娘の来訪者。「女性でもできる農業」というキーワードを通じて、農業の裾野を広げていく姿勢は、まさに“地域リーダー”としての姿です。
単に生産するだけではなく、「教える」「伝える」「共有する」ことが、農業を産業として持続可能にする要因の一つです。こうした人とのつながりが、農業における“やりがい”であり“希望”でもあると感じました。
まとめ:農業の未来は、現場の「言葉」と「行動」から始まる
今回の吉村農園さんの動画は、単なる「作業報告」ではありませんでした。そこには、これからの農業を考える上で重要な要素がいくつも内包されており、まさに“未来への布石”とも言える貴重な発信でした。
まず目を引いたのは、気候の変化に対する驚くべき柔軟性です。「5月は春ではなく“涼しい夏”だ」と言い切るその一言には、現場を知る者にしか持ち得ないリアリティが込められています。教科書やマニュアルではなく、実際の温度、日射、湿度、作物の様子を見て判断する。この“感覚と経験に裏打ちされた理論”こそ、今の農業に最も必要な視点だと感じました。
さらに、病害虫管理におけるリスク判断も実に現実的でした。全てをコントロールしようとするのではなく、「防げること」と「防げないこと」を分け、その上で最も有効な一手を選ぶ。この割り切りと判断力は、あらゆる経営判断に共通するスキルであり、農業という現場においても極めて重要です。
また、生産方法の刷新として、育苗でのポット導入に踏み切った点は、ただの技術選定ではありません。これは、既存のルーティンにとらわれず「変える勇気」を持ち、改善を継続する姿勢の表れです。農業を含むあらゆる業種において、時代や環境に応じて“アップデート”する姿勢こそが生き残りの鍵となります。
加えて、現場で得た販売のヒントにも注目です。イベント会場での他業者の販売方法から学びを得る姿勢は、マーケティングにおける現場力の象徴です。「良いものを作れば売れる」という時代は終わり、「どう伝えるか」「どう体験させるか」が勝負の時代において、この柔軟な観察力と吸収力は、農家でありながらも立派な経営者の資質だと感じました。
そして何より感動的だったのは、人との関わりから生まれるやる気です。農業は一見すると孤独で、閉ざされた職業のように映るかもしれません。しかし、訪問者との対話、農家同士の情報交換、現場の共有──そうした“つながり”の中からこそ、情熱は再燃し、新しい希望が芽吹くのです。
こうした全ての要素──柔軟性・判断力・改革・販売視点・人との絆──は、どれも「現場」からしか生まれません。そして、その現場の“声”を言葉にして伝えていく人がいるからこそ、農業は「孤独な仕事」から「つながる仕事」へと変わっていきます。
吉村農園さんのように、知識と経験、そして行動力を持ち、発信する農業者が増えることは、地域を越えて日本の農業全体にとっての希望です。今後の取り組みや挑戦、そして次世代を巻き込んだ農業のアップデートに、心から期待したいと思います。
農業の未来は、机上の空論ではなく、「現場の言葉と行動」から、確かに始まっているのです。
🔗 参考元動画はこちら(YouTube)
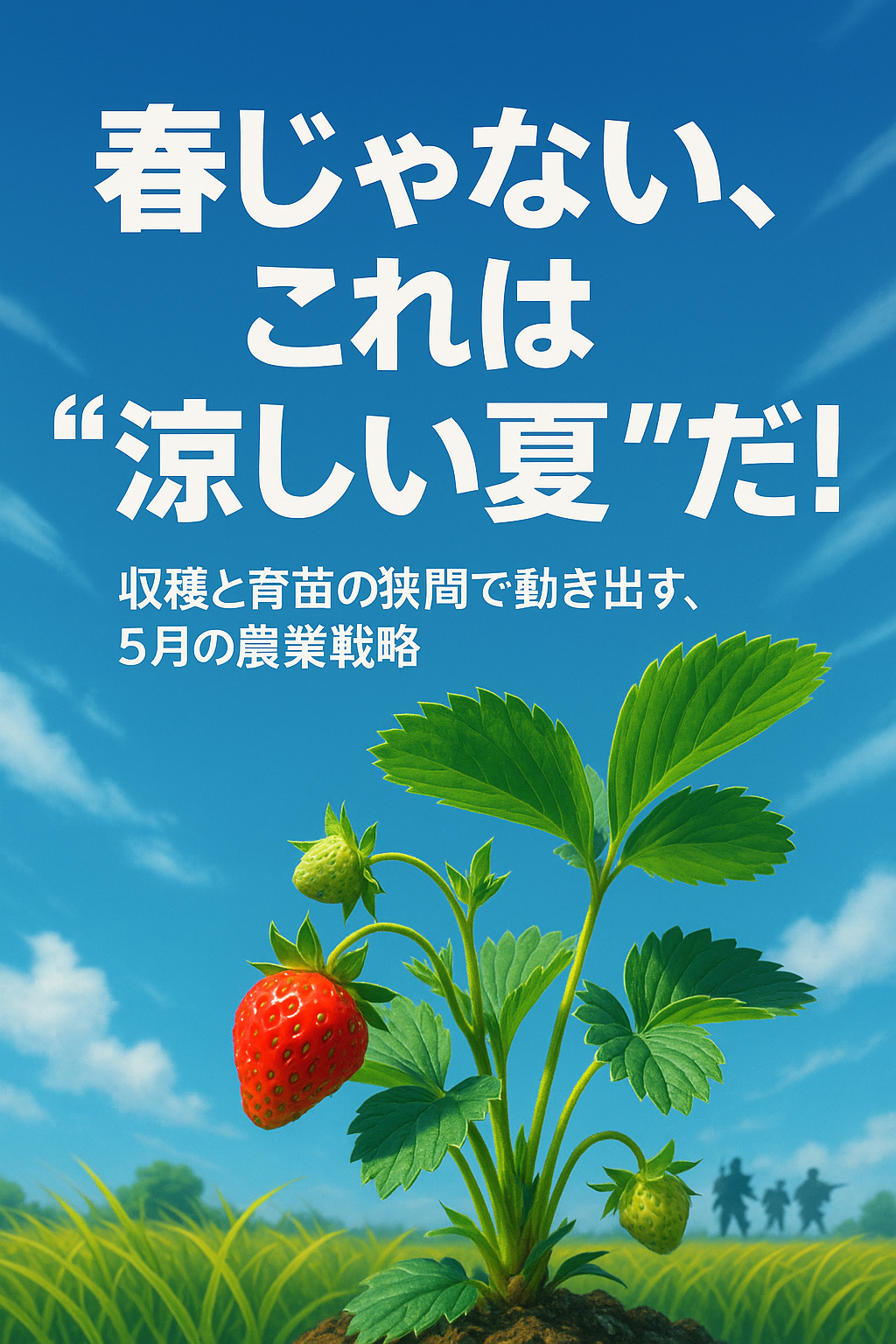






コメント