【衝撃の事実】「補助金漬け」のウソと農業切り捨ての現実──我々が“知らされていない”国家戦略の闇
今回ご紹介したいのは、東京大学の鈴木宣弘特任教授が出演された政経プラットフォームの番組「日本の農家は補助金漬け? その裏にある衝撃の実態!」です。私も長年、政策分析や産業構造改革の現場に身を置いてきましたが、ここまで赤裸々に語られた「日本農業の真実」には、正直言って震えました。
今、日本の農業を語る上で避けて通れないキーワードがいくつかあります。それが「補助金」「自給率」「農業の高齢化」「国際競争」「グローバル企業」、そして「安全保障」です。これらが互いに複雑に絡み合いながら、日本の農業を静かに、しかし確実に追い詰めている。その全体像を、今回の鈴木教授の話は明確に浮かび上がらせました。
■「補助金漬け」農家という幻想
まず本題、「日本の農家は補助金漬けで甘やかされている」という論調について。これ、事実とまったく逆です。番組内でも出てきましたが、米農家の実際の収入は、補助金を差し引いて時給換算でたったの10円。赤字でも農業を続ける方々の多くは、年金や兼業の収入を注ぎ込んでいるのが現状です。
「補助金があるから楽をしている」どころか、「補助金があっても暮らせない」ほど追い詰められているのです。この矛盾が、なぜ放置されてきたのか?
■戦後から続く「食の属国」戦略
鈴木教授が明言されていた通り、日本は戦後一貫して「アメリカの在庫処分先」として食料政策を捻じ曲げられてきました。小麦が余れば「米を食うとバカになる」というデマまで動員し、国民の胃袋をアメリカ産の農産物で満たそうとした。これはもはや陰謀論ではなく、歴史的事実です。
その結果、日本の農業は構造的に破壊され、「食料の自給率」はカロリーベースで38%、穀物に至っては28%。平時はよくても、戦争や外交的衝突が起これば、「日本人が餓死するシナリオ」は現実になり得ます。
■「保護」ではなく「放置」されてきた農業
海外と比較しても明らかです。フランスなどでは農家の所得の100%、場合によっては200%以上が補助金。これは「彼らが怠け者だから」ではなく、食料供給を国家安全保障と見ているからです。
それに対し、日本では農業所得に占める補助金の割合はわずか約30%。しかも、その額すらも「削減対象」とされ続けています。
「守られている」はずの農業が、なぜ衰退しているのか? 答えは明白です。「守られていない」からです。
■農業を犠牲に、工業で稼ぐ「国家トレード」
日本政府は長らく、農業を犠牲にすることで工業製品──とりわけ自動車を海外に輸出し、「金を稼ぐ」という構造を取ってきました。
鈴木教授いわく、大型貿易協定1本につき、自動車産業は3兆円の利益を得て、農業は真っ赤な赤字を計上してきた。要するに、国家ぐるみで「農業を切り捨てて金を稼ぐ」構図が続いてきたわけです。
その代償として、自給率は下がり、地域社会は崩壊し、農業は高齢者ばかりとなり──。それでもなお、メディアは「農業は保護されすぎ」と言い続ける。その背後には、情報操作の意図が透けて見えます。
■「農業がなくなれば国がなくなる」──安全保障としての農業
極めて重要なのは、農業は単なる“産業”ではなく、「国を守るための装置」であるという点です。
まず食料安全保障。戦争や貿易制裁で輸入が止まれば、食料供給は即座に途絶します。自給率が3〜4割という国は、平時には問題なくても有事には“飢える国”になります。
もう一つは国土防衛。国境付近の農村が崩壊すれば、そこは「無人地帯」になり、外国勢力が入り込む可能性が高まる。実際、世界の紛争地帯は“無人の田畑”が突破口になることが多い。
農業とは「胃袋」と「国境線」の両方を守る国家装置なのです。これは単なる“農業従事者の話”ではありません。我々国民全体のサバイバルに関わる問題です。
■結論:農業を軽視すれば、国家が沈む
東京大学・鈴木宣弘教授の話を通じて、私は一つの揺るぎない確信を得ました。
「日本が本当の意味で再生するには、“農業の再建”が不可欠である」
これは単なる感情論ではありません。国家が自らの胃袋を守れないということは、すなわち国防が成り立たないことを意味します。たとえ最新鋭の兵器を揃えても、戦わずして飢えて倒れる国に未来などないのです。食料の自給体制を立て直すことは、「国を守る」ための最も根幹的な戦略です。
■「補助金は無駄」ではない──国家への投資である
農業に投入される補助金を、「税金の無駄遣い」「甘やかし」と切り捨てる風潮があります。しかし、それは本質を見誤った見方です。
諸外国、特に欧州の主要国では、農業への補助金は当たり前のものとして“国家防衛費”と同じ意味を持っています。農家を保護することは、国民の生命線を守ることに他ならないからです。フランスの農家の中には、補助金がなければ“農薬や肥料すら買えない”という状況もあるにも関わらず、国家はそれでも彼らを守る。それは、農を失うことが国家の敗北につながると理解しているからです。
我が国も、農業に対する支出を「消費」ではなく「未来への投資」として考え直す必要があります。
農家を「支えられる側」ではなく、「国を支える側」と位置づけ直すことが必要です。
それは単に農業だけの話ではなく、食料・環境・地域・安全保障すべてに直結しています。
■情報操作に騙されず、事実と向き合う政治へ
「農家は保護されすぎ」「農産物は高すぎて非効率」…これらの言説が、どれほど意図的に流され、どれほど多くの国民を“誤解”させてきたか。
その裏には、大規模な貿易構造やグローバル企業の戦略、そして外圧に迎合し続けた日本政府の姿があります。食料の輸入自由化が進み、日本人の胃袋はいつの間にか外国依存になった。その間に、我々は「農を守ること=悪」という奇妙な価値観をすり込まれてしまったのです。
しかし、今こそ目を覚まさねばなりません。
“現実”は明らかです。
農家の多くは時給10円で働き、年金や副業収入をつぎ込んで、「国のために」米を作っているのです。
それを、「補助金漬けの怠け者」と切り捨てて良いはずがありません。むしろ、この国の最後の砦となっているのが、彼らです。
■私たち国民こそが、食を守る当事者である
最後に申し上げます。
国家のあり方は、政治家だけが決めるものではありません。主権者は私たち一人ひとりです。
だからこそ、我々ができることは、
- 「現実を知ること」
- 「声を上げること」
- 「意思を持って選ぶこと」
この3つに尽きます。
目先の価格の安さやメディアの情報に流されるのではなく、「この国の未来にとって何が必要か」という本質を、自らの頭で考え、行動することです。
農業を切り捨てるということは、
私たち自身の命を切り捨てることに等しい。
国民が“消費者”であるだけでなく、“生活者”として、“主権者”として、食と農に向き合うべき時代が来たのです。
これは、鈴木教授の警鐘ではなく、「我々への最後通牒」だと受け止めるべきでしょう。
農業を軽視すれば、国家が沈む。
その未来を変える力は、我々一人ひとりの「関心」と「行動」にかかっています。
🔗 参考元動画はこちら(YouTube)
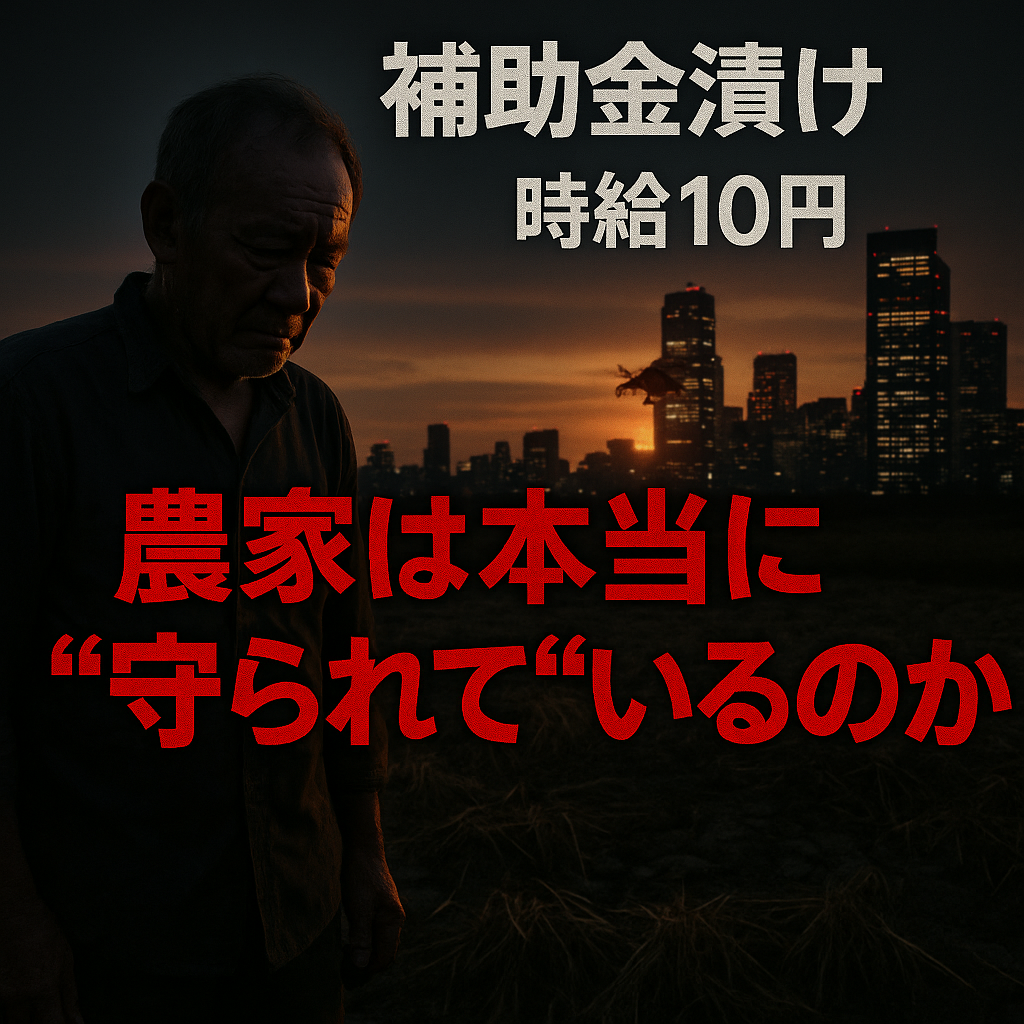





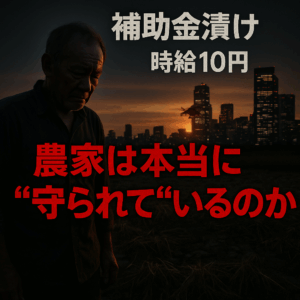
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] [1] https://niwa-ichigo.com/%E3%80%8C%E8%BE%B2%E5%AE%B6%E3%81%AF%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E6%BC%AC%E3%… […]